コラム

通夜は、葬儀や告別式の前日に執り行われる、参列者が故人を偲んで過ごす大切な儀式です。
では、式の規模を抑えて行う家族葬では、通夜はどのように実施されるのでしょうか?
本記事では、家族葬における通夜の基本的な流れを整理し、執り行う際に気をつけたいマナーや注意点を解説します。
家族葬であっても、喪主が希望しない限りは通夜を執り行うのが一般的です。
通夜を行う場合は、1日目に通夜、2日目に葬儀・告別式・火葬という流れになり、一般葬の流れと大きく変わりません。
しかし近年では、「精神的・身体的な負担を抑えたい」「遠方からの参列者が多く2日にかけて行えない」などの理由から、通夜を省略するケースも増えています。
その場合には、後ほど詳しく紹介する“一日葬”や“火葬式”といった葬儀形式を選ぶことになります。
いずれの形式にも、執り行うにあたって注意点があるため、ご家族と十分に話し合ったうえで決めることが大切です。
関連記事:家族葬とは?参列者の範囲や費用、事前の確認事項を解説
ここでは、家族葬の通夜の流れを、場面ごとに分けて紹介します。
家族葬を初めて執り行う場合でも、以下の内容を把握しておけば、参列者をスムーズにお迎えできます。
【家族葬における通夜の流れ】
はじめに、式場に到着した参列者の受付を行います。
芳名帳に名前や住所の記帳を促し、この場で香典を受け取りましょう。
受付を済ませた方には、お礼状とともに通夜返礼品をお渡しします。
通夜返礼品は、食品や日用品といった消耗品を贈るのが一般的です。
なお、喪主や故人の直系の親族は、式中に遺族席を離れることができません。
そのため、受付役には直系以外の方から選ぶ必要があります。
もし適任者がいない場合は、葬儀社のスタッフに依頼することも可能です。
費用は別途かかりますが、葬儀のプロが丁寧に対応してくれるので、安心して任せられます。
通夜がはじまると、僧侶による読経が始まります。
その際に、喪主・ご家族・親族・故人のご友人の順に、故人との関係が近い方から焼香を進めていきます。
家族葬では参列者の人数が限られるので、焼香に時間をかけながら、故人との最後のひとときをゆっくりと過ごせるのが特徴です。
全員の焼香を終えたら、僧侶の説法や法話を聞き、最後に喪主から通夜を閉じる言葉が述べられます。
家族葬では、形式的な挨拶が省略されるケースもありますが、その場合も参列者に感謝の気持ちを伝えるひと言を添えるとよいでしょう。
通夜法会が終わったあとは、参列者に食事やお酒をもてなす“通夜振る舞い”を行うのが一般的です。
通夜振る舞いでは、参列者や僧侶への感謝を伝えるとともに、故人との思い出を語り合います。
お開きの際には、喪主から葬儀や告別式の日時を改めて伝えておくと親切です。
なお近年、家族葬では通夜振る舞いを省略することも少なくありません。
関西、大阪の風習では、一般葬の場合でも、一般の参列者へ通夜振る舞いをするケースは非常に珍しく、親族や親戚にのみ振る舞うことが一般的です。
ですので、関西では家族葬であっても、親戚が弔問に来る場合においては通夜振る舞いを省略するケースは稀です。
とはいえ、無理に慣習にこだわらず、ご家族の意向を尊重したかたちを選ぶことが大切です。
家族葬で通夜を滞りなく執り行うために、事前に知っておきたいマナーがあります。
問題なく式を迎えられるよう、以下のポイントを確認しておきましょう。
家族葬の場合は、訃報を送る際に通夜は近親者のみで執り行う旨をきちんと伝えることが大切です。
この部分をきちんと伝えられていないと、呼ぶのを控えた方が誤って訪れてしまう可能性があります。
そのため、訃報を送る方には、今回の葬儀に呼んでいるのか否かが明確にわかるように伝えましょう。
なお、訃報を伝える前に家族葬を実施した場合には、参列していない方にその旨を伝えます。
報告する際は、家族葬で執り行った旨とあわせて、故人の逝去日や喪主の氏名、問い合わせ先などを葉書やメールで案内すると丁寧です。
家族葬の通夜で香典や供花、弔電の受け取りを辞退する場合には、必ず事前に知らせておきましょう。
近年は、「参列者に気を遣わせたくない」という理由から、これらを辞退するご家族も少なくありません。
その際は、訃報の案内とあわせて「香典・供花はご遠慮いたします」と明記しておくと、参列者との行き違いを防げます。
家族葬の通夜では、参列者側にも守るべきマナーがあります。
なかには、参列者から「どのように振る舞えばよいか」と尋ねられる可能性もあるため、以下で確認しておきましょう。
【家族葬における通夜での参列者側のマナー】
繰り返しになりますが、家族葬では通夜に参列できる方が限られています。
参列する方は、訃報に「参列はご遠慮ください」といった記載がないかを必ず確認しましょう。
辞退の案内がある場合は、参列せずに故人を静かに偲ぶのがマナーです。
一方で、通夜の詳細が案内されている場合や、ご家族から直接参列をお願いされた場合には、参列しても問題ありません。
この場合は、参列したくてもできない方のことを考慮し、参列することを周囲に話したり、訃報を広めたりするのは控えるべきです。
家族葬の通夜での服装は、一般葬と同様にブラックフォーマルが基本です。
男性は黒のスーツに白いワイシャツを合わせ、ネクタイ・靴下・靴も黒で統一します。
女性は黒のスーツやワンピース、アンサンブルを選び、シンプルで落ち着いた装いを心がけましょう。
アクセサリー類は男女ともに最小限にとどめ、華美なものは避けるのが望ましいです。
なお、学生の場合は、制服で差し支えありません。
家族葬の通夜であっても、喪主が辞退を表明しない限りは、香典を持参するのが一般的です。
ただし、式場で香典辞退の案内があれば、無理に渡さずに持ち帰るのがマナーといえます。
また、供花や弔電についても同様に、辞退の有無を確認しておきたいところです。
ご家族の意向に反して供花を贈ると、その扱いやお礼状の準備などのために、かえって負担をかけてしまうことがあります。
家族葬の通夜でご家族にお悔やみの言葉を伝える際にも、注意が必要です。
親しい関係であっても、悲しみを長々と語ったり、思い出話に深入りしたりすると、ご家族の心労を増やしかねません。
また、お悔やみの言葉を伝えるときは、“忌み言葉”の使用にも注意したいところです。
忌み言葉とは、不幸の連続を連想させる“重ね言葉”や、死を直接的に表す表現のことを指します。
“死ぬ”“生きる”などの表現は避け、“ご逝去”“ご生前”など、やわらかな表現に言い換えましょう。
家族葬にやむを得ず参列できない方や、参列者として呼ばれなかった方もご家族に失礼のない方法で気持ちを伝えることが大切です。
ご家族としても、参列を辞退した方から「代わりにどのように気持ちを伝えればよいか」と尋ねられることもあるため、以下の内容を知っておくと安心です。
家族葬に参列できない場合でも、「せめて供花や弔電を送りたい」と考える方も少なくありません。
その際には、まずご家族が受け入れているかどうかを確認することが不可欠です。
ご遺族から「供花や弔電は歓迎します」との返答があれば、マナーに沿って手配します。
特に供花は、祭壇全体の色合いや雰囲気を配慮する必要があるため、喪主に色味を確認するか、葬儀社を通じて手配しましょう。
家族葬に参列できない場合でも、後日に改めてご自宅を訪問し、線香をあげて弔意を伝えることもできます。
ただし、その際には必ずご家族の承諾を得たうえで、都合が良い日時に伺いましょう。
また、線香だけでなく、簡単な手土産やお花を添えるとより丁寧な印象になります。
このように事前の配慮を重ねて行動することで、故人を偲ぶ気持ちがご家族にもきちんと伝わるはずです。
家族葬で通夜を行う際には、参列者に対しての配慮と心遣いが欠かせません。
本項では、家族葬の通夜を執り行う際に意識しておきたいポイントを紹介します。
【家族葬の通夜で意識するポイント】
家族葬の通夜は、故人のご家族や親族、親しかったご友人でささやかに執り行う儀式です。
参列者一人ひとりに丁寧に対応し、落ち着いて故人を偲べる雰囲気を整える必要があります。
喪主をはじめ、ご家族は式場の入口で参列者を迎え入れ、感謝の気持ちを伝えましょう。
参列者との会話では、故人の人柄や思い出を共有し、互いに励まし合うことで温かな時間が生まれます。
また、高齢者や体調が優れない方が参列する場合には、出入口付近に席を設けたり、移動の際に付き添ったりと、負担を減らすための配慮も欠かせません。
通夜後に通夜振る舞いを行うかどうかは、喪主の判断に委ねられます。
通夜振る舞いを行う場合は、豪華な料理を用意する必要はなく、簡素な内容で十分です。
ただし、会食の準備や対応は、ご家族にとって大きな負担になることもあります。
参列者の人数や体調、予算などを考慮し、無理のない範囲で検討しましょう。
通夜振る舞いを省略する際には、その旨や経緯を参列者に伝え、理解を得ることが大切です。
なお、その際にはお茶や軽食を添えるだけでも、参列者への心遣いになります。
家族葬では、参列や香典・供花などを辞退していても、当日に参列希望者が訪問したり、香典や供花が届いたりすることがあります。
そのような場合には、無理にお断りせず、気持ちを尊重して快く受け入れることが望ましい対応です。
辞退の意思を示していたからといって無理に拒むと、トラブルにつながりかねません。
参列希望者や香典・供花を贈ってくださった方の弔意を配慮し、できる限り受け入れる姿勢を心がけましょう。
先述した通り、家族葬では通夜を行わないケースもあります。
以下では、通夜を省略する家族葬の形式を2つ紹介します。
一日葬とは、通夜を省略し、葬儀・告別式・火葬を1日で行う葬儀形式のことです。
通夜が省かれる点を除けば、通常の家族葬と大きく変わりません。
一日葬では、儀式を短期間で済ませられるため、複数日にわたり準備や参列を続ける必要がなく、心身への負担を抑えられます。
また、遠方からの参列者も宿泊を伴わずに済むのも負担を減らすポイントです。
一方で、1日に省略したがゆえに、その日にほかの予定がある方は故人との最後の別れに立ち会えないという懸念点もあります。
火葬式は、通夜と葬儀・告別式を省略し、火葬のみを執り行う葬儀形式です。
故人を安置施設や自宅などにお迎えし、そのあと火葬場へ移動して火葬を執り行います。
通夜や告別式を行わないため、式場の使用料や返礼品・接待費用が不要となり、費用を大幅に抑えられる点が大きなメリットです。
しかし、故人とのお別れの時間が十分に取れないので、周囲の方々からの理解が得られにくいかもしれません。
また、宗派や寺院によっては儀式を伴わない葬儀を認めておらず、菩提寺(ぼだいじ)から納骨を断られるケースもあります。
火葬式を検討する際は、ご家族や親族に意向を共有し、菩提寺の規則をご確認ください。
家族葬で通夜を省略すると、さまざまな負担を減らせる反面、周囲への配慮や準備を怠るとトラブルの原因になりかねません。
また葬儀社のプランによっては故人との最期の夜をゆっくり過ごせない場合もあり、結果的に親族が後悔されるケースも少なくはありません。
後悔しないためにも、以下の注意点を確認しておきましょう。
【家族葬で通夜を省略する際に気をつけたいこと】
菩提寺がある場合には、通夜を省略したい旨を伝えて了承を得ることが欠かせません。
仏教的な観点では、通夜は“死者を弔うための重要な儀式”と位置づけられているためです。
実際に、通夜を行わなければ納骨ができないと定めているお寺も存在します。
後々のトラブルを防ぐためにも、菩提寺と事前に相談することが重要です。
通夜を行わないときは、菩提寺だけでなく、ご家族や親族からも理解を得る必要があります。
一日葬や火葬式といった形式は、従来の葬儀を簡略化した新しいスタイルなので、なかには抵抗感がある方も少なくありません。
通夜を行わない理由をきちんと説明し、礼儀を尽くす姿勢をみせることで、納得を得やすくなります。
通夜を省略すると、後日の弔問対応に追われるリスクがあることも念頭に置いておきましょう。
一般葬では、参列者の人数制限が設けられないことが多く、通夜か告別式のいずれかに参列できる環境が整っています。
しかし、家族葬では人数を限定して執り行うため、さらに通夜を省略するとその日に都合が合わない方は参列の機会がありません。
その結果、後日あらためて自宅へ弔問に訪れる方が増え、かえってご家族の負担が増える可能性があります。
家族葬でなおかつ通夜を省略する場合は、当日の進行だけでなく後日の対応まで想定しながら準備することが不可欠です。
通夜を省略する家族葬を検討する際は、葬儀社のプランもよくご確認ください。
費用や式場利用の条件に思わぬ制約があると、希望通りの葬儀が実現できない可能性があります。
確認しておきたい主な項目は、以下の通りです。
【通夜を省略する家族葬を依頼する際に確認するポイント】
上記のポイントを事前に確認しておくことで、追加費用や想定と異なる進行などのトラブルを防げます。
通夜を省略すること自体は決して悪いことではなく、ご家族にとって最善のかたちを選ぶための一つの方法です。
だからこそ、周囲への配慮と十分な準備を忘れずに進めることを心がけましょう。
家族葬で通夜を執り行う際は、マナーや意識するべきポイントを事前に把握しておくことで、参列者を安心してお迎えできます。
一方で、通夜を省略する場合は、一日葬や火葬式といった葬儀形式を選びます。
これらは負担や費用を抑えられる反面、いくつか注意すべき点もあるため、慎重に検討することが欠かせません。
ご家族の希望や参列者への配慮を踏まえたうえで、納得のいく葬儀を執り行いましょう。
大阪エリアで家族葬を検討されている方は、「家族葬おくりみ」にぜひご相談ください。
通夜を省略した家族葬の実施にも対応しており、費用や規模、参列者への対応など細かなご要望に合わせて最適なプランをご提案いたします。
株式会社川上葬祭 代表取締役
<資格>
<略歴>
創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。
ご葬儀は大切な儀式であり、プランや費用は様々です。事前相談をお勧めいたします。
事前にどのようなお葬式にされたいのかご認識いただくことで、いくら掛かるのかが明確になり、ご不安が解消されます。不必要な物を取り除くこともできます。
事前相談ではご家族様のご希望やご相談を丁寧にお伺いする事が出来ます。その物語からわたしたち「家族葬おくりみ」のスタッフが世界で一つだけのお別れの刻を提案いたします。
よくあるトラブルに「見積より支払い金額が多くなった」「希望の葬儀と違った」ということがあります。事前相談で金額、内容が適切かどうかチェックすることができます。
ご家族様に最適な資料をお送りさせていただきます。資料は葬儀社とわからない、無地の封筒でお送りすることもできますので ご安心ください。またいただいた個人情報は資料の送付とその確認の際のみに利用させていただきますので ご安心くださいませ。
資料請求で届くもの
お葬式プラン / 式場のご案内 / ことほぎ友の会のご案内 等
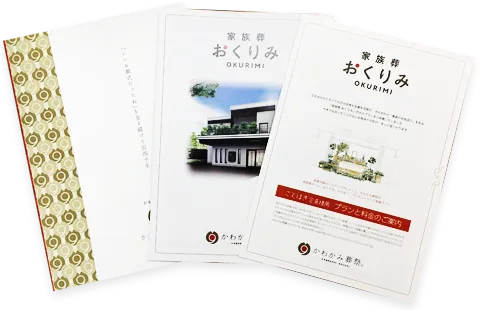

ご来店以外にご希望場所までお伺いする事も可能です。その際ご指定場所をお知らせ下さい。

お電話にて不明な点等ご相談承っております。24時間365日いつでもご対応させて頂きます。

メールでもお気軽にご相談いただけます。まずは不安や疑問点から一緒に解決しましょう。
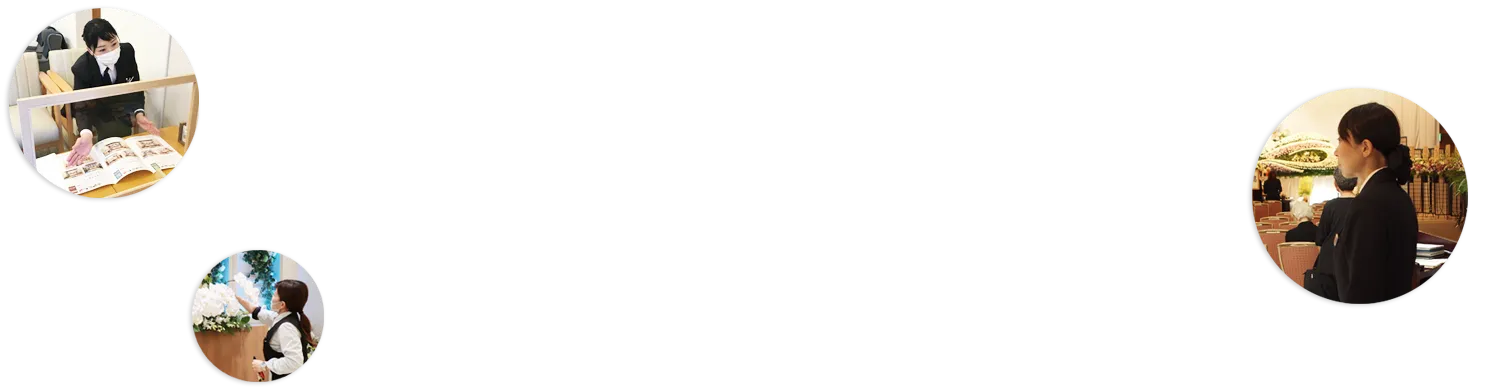
私たちは、常に、お客様の立場に立ち、喜んでいただけるご葬儀を提案・実現いたします。
品質の確かなお葬式を、地域の皆様にご提供しております。
式場においては、1日1組の葬儀式場で、気を遣うことのないゆっくりとした大切な人とのお別れをご提供しております。
価格においては、不透明なお葬式費用を無くし、明朗会計を実施してまいりました。
おくりみは、今後もお客様に喜んでいただくことを第一に、日々、精進してまいります。
大阪市|東住吉区・天王寺区・生野区の、家族葬・お葬式の相談窓口は「おくりみ」へ。JR桃谷駅から徒歩5分。桃谷商店街からもアクセスが便利な「桃谷本店」 今里筋と勝山通の交差する大池橋交差点、大池橋バス停の目の前「大池橋店」お葬式や家族葬の相談、事前の費用見積り、準備や手続きのこと承ります。
無料のお持ち帰り資料(生野区優良葬儀場パンフレット、お葬式の手引き、お葬式のマナー他)を多数、取り揃えております。
最寄り駅:生野区の各駅・・・JR桃谷駅、鶴橋駅、東部市場前駅、近鉄・鶴橋駅、今里駅、大阪メトロ千日前線鶴橋駅から乗り継ぎアクセス良好。