コラム

葬儀社は近年、ご家族の要望に応じてさまざまなかたちの葬儀に対応できるようになりました。
“家族葬”もそのうちの一つとして知られていますが、具体的にどのような流れで執り行うのかまでは知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、家族葬の流れとメリットを、円滑に進めるためのポイントとともに解説します。
葬儀当日、心安らかに故人様を送り出せるよう、本記事を参考にしてみてください。
まずは家族葬がどのような葬儀なのかを理解するために、以下に記した家族葬と一般的な葬儀の特徴を見比べてみましょう。
【家族葬と一般的な葬儀の特徴】
| 葬儀の種類 | 家族葬 | 一般的な葬儀 |
| 参列者 | ・ご家族 ・親族 ・故人様と親しかった友人 |
・ご家族 ・親族 ・故人様と親しかった友人 ・近隣の知人 ・仕事の関係者 |
| 参列者の人数 | ~30人程度 | 30人以上 |
| 斎場(式場) | 比較的小さめ | 広い |
| 葬儀の内容 | 決まった形式がない | ある程度決まった形式がある |
上記の通り、家族葬は一般的な葬儀と比べて比較的小規模であることが特徴です。
主な参列者はご家族や親族、故人様と親しかった友人で、家族葬のプランを提供する多くの葬儀社では30人までの規模を想定しています。
一般的な葬儀では、近隣の知人や仕事の関係者が参列することも視野に入れるため、人数は30人以上が想定されています。
参列者が少ない家族葬ですから、広い斎場(式場)を利用する必要がありません。
一般的な葬儀と比べて多くの参列者への配慮も不要となるので、葬儀のスタイルも柔軟に決めやすくなるわけです。
このような特徴から、家族葬は比較的小規模で行われる自由度の高いかたちの葬儀といえます。
関連記事:家族葬とは?参列者の範囲や費用、事前の確認事項を解説
故人様のご逝去後、家族葬を行う際は短い時間のなかで多くの選択を急がなければなりません。
もちろん葬儀の段取りは葬儀社の担当者に主導してもらえますが、あらかじめ流れを把握しておくと、よりスムーズに家族葬を進めるのに役立ちます。
ここからは、故人様がご逝去されたのちに家族葬を行う際の流れを、以下の項目ごとにお伝えします。
なお、決まった形式がない家族葬は、これらの流れを一部変更して執り行うことが可能です。
【家族葬の流れ】
故人様のご臨終後は医師から死亡届を受け取り、すみやかに葬儀社を手配して、ご遺体を病院から自宅や斎場などの安置場所へ搬送してもらいましょう。
このとき、病院から葬儀社を紹介されることがありますが、必ずしもその葬儀社に依頼しなければならないというわけではありません。
家族葬は、ご家族の意向を反映して柔軟に対応できる葬儀であるため、納得のいくかたちで執り行うには、ご自身で選定した葬儀社に依頼するほうがよいといえます。
搬送から家族葬まで一貫して依頼できる葬儀社を選べば、よりご家族の意向に沿った葬儀を執り行うことが可能です。
なお、葬儀社にはご遺体の搬送・安置のみを依頼することもできます。
家族葬を依頼する葬儀社の選定がお済みではない場合は、病院から紹介された葬儀社に一旦搬送・安置を依頼して、葬儀社の選定に移ることも考えてみてください。
葬儀社に搬送を依頼したあとは、家族葬に参列してほしい方にのみ連絡をしてください。
家族葬は一般的な葬儀とは異なり、連絡をした方以外の参列を控えてもらうことになるため、連絡した方にはその旨も同時に伝えておきましょう。
また家族葬では、葬儀の規模を考慮して香典や供物、供花を辞退することもあります。
特定の人物からのみ受け取るとトラブルとなりかねないため、家族葬を執り行う場合は、香典に関する取り決めを参列者にあらかじめ伝えておくことが必要です。
ご遺体を搬送・安置し、参列者への連絡が完了したあとは、葬儀社とともに以下の内容を決定していきましょう。
【家族葬の打ち合わせ内容】
まずは、火葬場の空き状況や葬儀に参列する宗教者の予定をもとに、家族葬を執り行う日時と斎場(式場)を決定します。
また葬儀社と話し合う際は、予算も伝えておくと、それに収まる範囲内でのプランを提案してもらえます。
打ち合わせを終えたら、葬儀社に故人様の着替えやお化粧といった身支度を整えてもらい、納棺をしていきます。
納棺時は、故人様の愛用品や旅立ちに際して持っていてほしいものを、副葬品として棺に納めることができます。
ただし、以下に該当する品物は副葬品として棺に納めることができない点に注意してください。
【副葬品として棺に納められない品物】
これらに該当する品物は、火葬および火葬後の収骨に支障をきたすおそれがあるので、たとえ故人様の思い出深い品であっても入れてはなりません。
故人様の遺影の前で参列者が弔問する通夜は、納棺後、以下のような流れで執り行われます。
【通夜の流れ(仏式の場合の一例)】
上記の通り、家族葬での通夜の流れは、一般的な葬儀と大きく異なる点はありません。
ただし、家族葬の参列者は数が限られるため、受付をご家族が行うことがあるほか、受付自体を設けないこともあります。
なお、通夜のあとに故人との思い出を振り返りながら食事をする通夜振る舞いは、関東を中心に行われている風習です。
関西にはこのような習わしはなく、ご家族や親族以外の参列者は焼香が終わったらすぐに帰宅するのが通例となっています。
通夜を終えた翌日に行う葬儀・告別式の流れは、以下の通りです。
【家族葬における葬儀・告別式の流れ(仏式の場合の一例)】
葬儀では、宗教者による読経や参列者の焼香が行われます。
故人様に最後の別れを告げる告別式が終わると閉式し、お棺の蓋を閉めて釘打ちを行い、火葬場へと出棺します。
火葬場に到着したら、炉の前で納めの式が行われます。
宗教者が同行する場合は、読経とともに焼香を行い、火葬へ移ります。
火葬が終わったら、遺骨を骨壺に納めるお骨上げを行い、家族葬は終了です。
続いて火葬・収骨後の流れは、以下の通りです。
形式の自由度が高い家族葬では、ご家族の意向に合わせてこれらを省略することもあります。
【火葬・収骨後の流れ】
※精進落としのタイミングは地域によって異なります。
初七日法要は、故人様が亡くなってから7日目に行われる法要のことです。
ご家族や親族、親しかった友人などが参列して故人様の冥福を祈るとともに、成仏を願う儀式です。
近年は、多忙で日時の調整が難しい場合や、遠方にお住まいで本来の初七日法要に合わせて再度集まるのが難しい場合を考慮して、葬儀と同じ日に行う傾向にあります。
葬儀と同日の初七日法要には、“繰り上げ初七日法要”と“繰り込み(式中)初七日法要”の2種類が存在します。
繰り上げ初七日法要は、告別式のあとに火葬を行い、再度葬儀場へ戻って行う初七日法要です。
一方、繰り込み(式中)初七日法要は告別式に続けて行うもので、繰り上げ初七日法要とは逆に、火葬前に行われるのが特徴です。
告別式のあと、同じ葬儀場ですぐに行うため、収骨後にすぐに解散となるケースが多いようです。
また、火葬の待ち時間に次項でお伝えする“精進落とし”を行うこともあり、関西ではこの形が一般的です。
精進落としは、故人様のご家族が葬儀のあとに、葬儀・告別式の参列者や僧侶を労うために用意する食事のことです。
四十九日の忌明けの際に執り行う風習でしたが、現代では葬儀当日に行うのが一般的です。
万が一、参列した宗教者が精進落としに参加できない場合は、食事の代わりとなる御膳料や持ち帰りの弁当をお渡しすることもあります。
葬儀後は、参列者からいただいた香典に対する気持ちを伝える、香典返しの手配を行います。
通常は四十九日法要が終わったあと、受け取った香典の額に応じて品物を決める“後返し”が主流です。
しかし家族葬では、香典の額に関係なく一律で事前に用意した品物を渡す“即返し”が一般的となっています。
ただし、いただいた香典が高額だった場合は、即返しでお渡しした品物が不相応となる場合もあるため、このようなときは、後日改めて香典返しの品物を贈るのがよいでしょう。
ここまで、家族葬の流れをご紹介しました。
一般的な葬儀とは異なり、式次第を柔軟に変更できる家族葬には、以下の3つのメリットがあります。
【家族葬のメリット】
家族葬への参列者は、親族をはじめとする身内が大半となるため、一般的な葬儀と比べて接待の負担を大幅に減らすことができます。
一般的な葬儀には、家族や親族、友人のほか、故人様が生前に仕事で関わりを持っていた方などが参加します。
特に仕事の関係者が参列した際には、失礼のないように振る舞う必要があるため、ご家族にとっては心身ともに大きな負担となりえるのです。
その点、家族葬の参列者は招待した方に限られるので、こうした負担を軽減できます。
ご家族のペースで故人様をゆっくりとお見送りできるのも、家族葬の大きな利点です。
先述したように、家族葬の参列者はご家族や親族のほか、親しかった友人に限られるため、思い出を振り返りながら故人様をゆっくりと偲ぶことができます。
一般的な葬儀のように、多くの参列者への対応に時間を取られることがないため、故人様の別れに向き合う時間を重視したい方は、家族葬を検討するのがよいでしょう。
家族葬は、一般的な葬儀と比べて費用を抑えやすいのが特徴です。
株式会社鎌倉新書が発表した「【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年)」によると、家族葬の費用の平均は105万7,000円でした。
同調査での、一般的な葬儀は161万3,000円となっており、家族葬と比べて55万円程度の差があります。
なお、費用の主な内訳はいずれも、以下の通りです。
【一般的な葬儀および家族葬にかかる費用の内訳】
| 基本料金(固定費) | ・斎場の利用料金 ・火葬場の利用料金 ・祭壇の設置費 ・棺の準備費 ・遺影の準備費 ・搬送費 |
| 飲食費(変動費) | ・通夜振る舞い ・精進落とし |
| 返礼品費(変動費) | ・香典のお礼の品物 |
これらの費用は、葬儀の規模によって大きく異なります。
家族葬は、通夜振る舞いや精進落としを省略する場合もあるため、上述の平均費用よりも、さらに抑えられることがあります。
ただし参列者が少なくなる分、香典が減るため、実質的な負担額が増える可能性がある点には注意しておかなければなりません。
参照元:鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」
さまざまなメリットがある家族葬ですが、円滑に執り行うためには以下の4つのポイントを押さえておくことが重要です。
【家族葬を円滑に執り行うためのポイント】
家族葬を行う際は、ご家族や親族などの理解を得ることから始めましょう。
家族葬は費用を抑えられる葬儀であるものの、ご家族や親族のなかには、一般葬とは異なる規模や形式に抵抗感を覚える方がいらっしゃることもあります。
無理に進めようとすれば、ご家族や親族間でのトラブルに発展してしまい、人間関係に亀裂が生じるおそれがあります。
このような場合は、ご自身の意向や状況を伝え、家族葬に対する理解を得られるように努めなければなりません。
皆が納得できるかたちで葬儀を執り行うことが、故人様を快くお見送りするポイントの一つです。
家族葬への参列者の範囲は、慎重に決定する必要があります。
参列者を決める際は、故人と深いつながりを持つ方や、今後も良い関係性を続けていきたい方を優先するのがよいでしょう。
ただし、故人様の交友関係が広かった場合は、参列を願う方がこのほかにも多くいらっしゃるはずです。
家族葬を選択したことでお別れを告げる機会がなくなれば、その方々に不満を抱かせるおそれがあります。
このような場合には、訃報連絡の際に家族葬を選んだ理由やご家族の意向を丁寧かつ明確に説明することが大切です。
その方が後日弔問を希望するのであれば、日時を調整して対応するように心がけると、不満の解消につながります。
菩提寺がある場合は、家族葬を執り行う旨をあらかじめ伝えておきましょう。
家族葬は、一般的な葬儀とは異なる形式で行うこともあるため、宗教者が当日の流れが把握できていないと、手違いが発生するおそれがあります。
こうしたリスクを防ぐためにも、家族葬を執り行うことを決定したあとは、まずはその旨にくわえて、具体的な流れについても伝えるようにしておくことが重要です。
参列してもらいたい方に訃報連絡を行う際は、家族葬である旨をきちんと伝えなければなりません。
特に参列者が限られる点を十分に説明しないと、お呼びする予定のない方にも訃報が伝わり、意図しない参列や供花に対応しなければならないといった事態が生じるのです。
そのため、参列してもらいたい方へ訃報連絡を行う際は、家族葬を執り行う旨にくわえて、なるべく他の方には伝えないでいてもらうようにお願いしましょう。
一方、お呼びしない方への訃報連絡は葬儀後に行い、弔問や香典、供花を望まない場合は、その旨もきちんとお伝えしてください。
このとき、家族葬を執り行った理由を聞かれる場合もありますので、丁寧に説明できるように準備しておくことが望ましいです。
家族葬を終えたあと、弔問がある場合は丁寧な対応を心がけてください。
都合が合わず家族葬に参列できなかった方や、訃報を聞きつけた方が、後日弔問に訪れることがあります。
弔問を辞退していない限りは、弔問者(会葬者)の故人に対する気持ちを汲み取って対応するとともに、感謝を伝えましょう。
家族葬で故人様を快く見送るためには、信頼できる葬儀社の選定が欠かせません。
ここからは、信頼できる葬儀社を選ぶ以下の3つのポイントをご紹介します。
【葬儀社を選ぶ際に見るべきポイント】
家族葬は自由度が高いため、故人様とそのご家族の意向に沿った内容で執り行うには、柔軟に対応してもらえる葬儀社を選ぶことが不可欠となります。
まずは、家族葬のプランを提供している葬儀社を探すところから始めましょう。
一般的な葬儀と比べて自由な形式で執り行うことができる家族葬は、予算やご家族の意向に合わせてさまざまなプランが用意されています。
そのため、段取りを決定していくなかで、複数の提案をしてくれる葬儀社は信頼できるといえます。
費用の見積もりが詳細かつ明確に示されているのかを細かく確認することも、信頼できる葬儀社を選ぶポイントの一つです。
葬儀社の説明が不十分な場合、打ち合わせ時点で聞かされていなかった費用がかかり、想定していたよりも高額になる場合があります。
打ち合わせの際は、各サービスにかかる費用を細かく確認し、その葬儀社が信頼に足るのかどうかを判断して依頼しましょう。
家族葬を安心して依頼できる葬儀社を選ぶためには、担当者の対応を確認しておくことも大切です。
なかには、費用を抑えられる家族葬を選んだことで、葬儀社の担当者の対応が変わることがあります。
故人様を快くお見送りするためにも、担当者の対応に違和感がある場合はその旨を伝えて、ほかの葬儀社を検討するのがよいでしょう。
最後に、家族葬で守るべきマナーをご紹介します。
家族葬におけるマナーは、一般的な葬儀と変わる点はありません。
服装は、故人様を偲ぶ気持ちを表現するために、必ず喪服を着用しましょう。
清潔感のある髪型を心がけるほか、結婚指輪や真珠のネックレスを除き、華美なアクセサリーの装着は避けるようにしてください。
また、動物を皮といった殺生を連想させる素材を使用したバッグや小物の使用を避けるのもマナーの一つです。
なお、喪服には紋付羽織袴の正式喪服や、光沢を抑えた黒いスーツの準喪服、グレーやネイビーなどを基調とした略喪服の3種類があります。
現代では、喪主は参列者と同様に準喪服を着るのが一般的です。
しかし、参列者のなかには遠方から訪問される方もいるため、略喪服でもよい旨をあらかじめ伝えておくと参列のご負担を軽減させることができます。
今回は、家族葬の流れとメリット、円滑に執り行うためのポイントを解説しました。
家族葬は、参列者がご家族や親族、故人様と親しかった友人などに限られた葬儀のことです。
一般的な葬儀と比べて小規模となるため、故人様をゆっくりと偲ぶことができるほか、費用を安く抑えられるというメリットがあります。
一方、慣習を重んじる方に抵抗感を与える可能性があるため、家族葬を行う際は、周囲に対して摩擦が起こらないよう丁寧な対応を心がけることが大切です。
大阪市内で家族葬を検討している方は、「家族葬おくりみ」へご相談ください。
専任のスタッフが葬儀に関する不安解消に努めるとともに、ご要望に合ったさまざまな葬儀プランを提案いたします。
株式会社川上葬祭 代表取締役
<資格>
<略歴>
創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。
ご葬儀は大切な儀式であり、プランや費用は様々です。事前相談をお勧めいたします。
事前にどのようなお葬式にされたいのかご認識いただくことで、いくら掛かるのかが明確になり、ご不安が解消されます。不必要な物を取り除くこともできます。
事前相談ではご家族様のご希望やご相談を丁寧にお伺いする事が出来ます。その物語からわたしたち「家族葬おくりみ」のスタッフが世界で一つだけのお別れの刻を提案いたします。
よくあるトラブルに「見積より支払い金額が多くなった」「希望の葬儀と違った」ということがあります。事前相談で金額、内容が適切かどうかチェックすることができます。
ご家族様に最適な資料をお送りさせていただきます。資料は葬儀社とわからない、無地の封筒でお送りすることもできますので ご安心ください。またいただいた個人情報は資料の送付とその確認の際のみに利用させていただきますので ご安心くださいませ。
資料請求で届くもの
お葬式プラン / 式場のご案内 / ことほぎ友の会のご案内 等
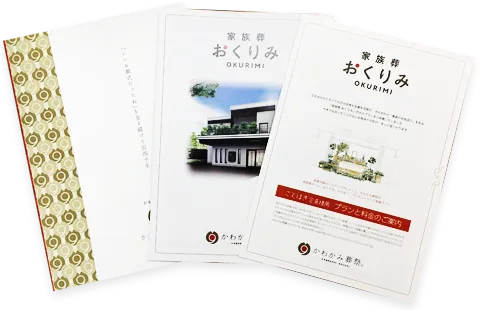

ご来店以外にご希望場所までお伺いする事も可能です。その際ご指定場所をお知らせ下さい。

お電話にて不明な点等ご相談承っております。24時間365日いつでもご対応させて頂きます。

メールでもお気軽にご相談いただけます。まずは不安や疑問点から一緒に解決しましょう。
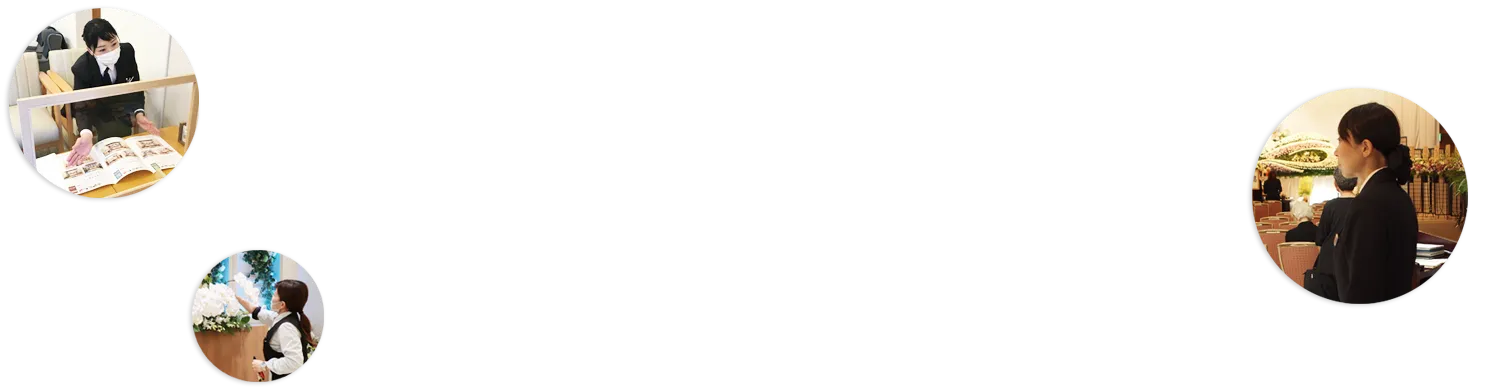
私たちは、常に、お客様の立場に立ち、喜んでいただけるご葬儀を提案・実現いたします。
品質の確かなお葬式を、地域の皆様にご提供しております。
式場においては、1日1組の葬儀式場で、気を遣うことのないゆっくりとした大切な人とのお別れをご提供しております。
価格においては、不透明なお葬式費用を無くし、明朗会計を実施してまいりました。
おくりみは、今後もお客様に喜んでいただくことを第一に、日々、精進してまいります。
大阪市|東住吉区・天王寺区・生野区の、家族葬・お葬式の相談窓口は「おくりみ」へ。JR桃谷駅から徒歩5分。桃谷商店街からもアクセスが便利な「桃谷本店」 今里筋と勝山通の交差する大池橋交差点、大池橋バス停の目の前「大池橋店」お葬式や家族葬の相談、事前の費用見積り、準備や手続きのこと承ります。
無料のお持ち帰り資料(生野区優良葬儀場パンフレット、お葬式の手引き、お葬式のマナー他)を多数、取り揃えております。
最寄り駅:生野区の各駅・・・JR桃谷駅、鶴橋駅、東部市場前駅、近鉄・鶴橋駅、今里駅、大阪メトロ千日前線鶴橋駅から乗り継ぎアクセス良好。