コラム

家族葬は、参列者の対応に追われることなく、故人をゆっくりと偲ぶことができるため、近年多くの方々に選ばれています。
しかし、一般葬とは異なる部分もあることから、「知らないあいだにマナー違反を犯してしまわないか?」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、家族葬で守るべきマナーを喪主と参列者、両者の視点で解説します。
家族葬とは、一般葬よりも比較的小規模に執り行う葬儀形式のことです。
家族葬を詳しく理解するために、まずは家族葬と一般葬の特徴を見比べて確認してみましょう。
【家族葬と一般葬の特徴】
| 葬儀の種類 | 家族葬 | 一般葬 |
| 参列者 |
|
|
| 参列者の人数 | ~30人程度 | 30人以上 |
| 斎場 | 比較的小さめ | 広い |
| 葬儀の内容 | 決まった形式がない | 決まった形式がある |
家族葬には、主にご家族や親族、故人と親しかった友人が参列します。
家族葬のプランを提供する多くの葬儀社では30人までの規模を想定しています。
一般葬では、近隣の知人や仕事の関係者が参列することも視野に入れるため、想定される人数は30人以上です。
このように参列者が少ない形式ですから、広い斎場を利用する必要はありません。
また、参列者が近親者に限られ、多くの参列者への対応に追われることがないことから、故人との最後の時間をゆっくりと過ごしやすい葬儀といえます。
関連記事:家族葬とは?参列者の範囲や費用、事前の確認事項を解説
葬儀を執り行うにあたって家族葬を選択する場合は、以下の5つの場面で、それぞれのマナーを守る必要があります。
【家族葬における喪主側のマナー】
家族葬を執り行う際は、その意向を親族にきちんと説明するように心がけましょう。
先述したように、家族葬は一般葬よりも比較的小規模で、参列者もご家族や関係の近い親族に限られます。
しかし親族のなかには、慣習にとらわれない家族葬と、一般葬との相違に抵抗感を覚える方がいらっしゃるかもしれません。
無理に進めようとすれば、ご家族や親族間でのトラブルに発展してしまい、人間関係に亀裂が生じるおそれがあります。
このような事態に陥らないためには、喪主側の意向や状況を丁寧に伝え、家族葬に対する理解を得られるように努めることが大切です。
家族葬に参列してもらう方の範囲は、喪主側の意向で自由に決定できます。
決められたルールはありませんが、2親等以内の親族や故人と特に親しかった友人などに参列してもらうのが一般的です。
しかし、故人と親しかった方が多くいらっしゃる場合は、その方々の気持ちにも配慮しつつ、参列者の範囲を慎重に決定しましょう。
家族葬を執り行う旨をお知らせする場合は、以下のような内容を記載します。
【家族葬のお知らせで記載する内容の一例】
まずは、喪主の意向を理解してもらうために、執り行う葬儀の形式が家族葬である旨を明記するとともに、参列の可否を明記してください。
特に参列してほしい方にお知らせする場合は、日時や場所を記載しましょう。
参列を控えていただきたい方にお知らせする場合は、その旨をきちんと記載しておくか、日時や場所を記載しないのも一つの手です。
香典を辞退する場合も、あわせて明記しておく必要があります。
近隣にお住まいの方へお知らせする場合は、町内会や自治体に回覧板で告知してもらうことで、家族葬である旨を説明する際の精神的疲労を軽減できます。
くわえて、故人が生前会社に勤務していた場合は、直属の上司や総務部に一報を入れておくことも大切です。
具体的にどのような対応をすべきなのかは、家族葬を依頼する葬儀社へ適宜相談するのがおすすめです。
家族葬の当日は、一般葬と同様に以下のような喪服を着用しましょう。
なお、喪主および故人と近い親族にあたる方は、正喪服を着用するのが一般的です。
【正喪服】
| 男性 | 洋装の場合はブラックフォーマルに黒のネクタイを締め、モーニングコートを着用。和装の場合は紋付羽織袴を着用し袴の紐は十字結びで、羽織紐や草履の鼻緒の色を黒に統一する |
| 女性 | 洋装の場合はブラックフォーマルのワンピースやアンサンブルを着用。和装の場合は染め抜き日向紋を5つあしらった黒無地の着物を着用し、黒い帯を結ぶ |
【準喪服】
| 男性 | 光沢のない黒いスーツを着用し、黒のネクタイを締める |
| 女性 | 光沢がなく、肌を露出しない黒・濃紺のワンピースやアンサンブル、スーツを着用する |
【略喪服】
| 男性 | 無地もしくはそれに近く、光沢がないダークグレー・紺のスーツを着用して黒のネクタイを締める |
| 女性 | 光沢がない黒・濃紺のワンピースやアンサンブル、スーツを着用する |
【子どもの服装】
| 乳幼児 | 黒を基調とした服を着用する |
| 保育園児・幼稚園児以上 | 制服を着用。なければ黒を基調とした服を着用する |
上記のいずれの服装であっても、派手な小物やアクセサリーは身につけず、清潔感のある身だしなみを心がけてください。
家族葬を執り行う際は、一般葬と同様に適切な場面で、適切なあいさつを行う必要があります。
家族葬で喪主のあいさつが求められる場面は、以下の通りです。
【家族葬で喪主があいさつをする場面】
まずは通夜や告別式の開始時に、導師や参列者へあいさつをします。
式を終えたら、参列者に向けて感謝の言葉を述べます。
精進落としの場を設ける場合は、親族に向けて労いの言葉を伝えましょう。
なお、喪主の意向で柔軟に執り行える家族葬では、あいさつの場を設けず、故人を静かに見送ることもできます。
ここからは、家族葬の参列者が守るべきマナーを解説していきます。
喪主側の方も、参列者から以下のマナーについて質問を受ける可能性があるため、きちんと把握しておきましょう。
【家族葬における参列者側のマナー】
家族葬へ参列するにあたり、まずは事前に受け取った案内状に香典や供花を辞退する旨が記載されているかどうかを確認しましょう。
一般葬よりも小規模な家族葬では、香典や供花の受け取りを辞退するケースが少なくありません。
辞退する旨が明記されているのにもかかわらず、香典や供花を用意すると、喪主側が想定していない対応に迫られることとなってしまいます。
そのため、辞退する意向を伝えられていた場合は、香典や供花を用意することはお控えください。
家族葬へ参列する際の服装は、一般葬と同様に準喪服を着用するのが一般的です。
喪主から「平服でお越しください」と伝えられている場合は、略喪服を着用しても問題ありません。
いずれの場合であっても、華美な小物の着用は控え、清潔感のある身だしなみで参列することを心がけましょう。
ご家族に向けたお悔やみの言葉は、受付での記帳時に伝えるのが一般的ですが、参列者が限られる家族葬では受付を設けていないこともあります。
この場合は「お悔やみ申し上げます」「このたびはご愁傷様です」と、お悔やみの言葉を喪主に直接伝えるのがよいでしょう。
なお、お悔やみの言葉を伝える際は、以下の“忌み言葉”を誤って使用しないように注意してください。
【忌み言葉の一例】
| 忌み言葉 | 使用してはならない理由 |
| 重ねる・重ね重ね・再三・くれぐれも | 不幸が重なることを意味するため |
| また・たびたび・しばしば・ますます | 不幸が再び来ることを意味するため |
| 死ぬ・死亡・四・九 | 苦しみや死を連想させるため |
故人と親しかった方のみが参列する家族葬で、細かな言葉選びのマナーを問われることはないかもしれません。
しかし上記は、故人のご家族に対して例外なく失礼にあたる表現であるため、お悔やみの言葉は慎重に選ぶことが大切です。
焼香の作法は宗派によって異なっており、参列者は故人の宗派に合わせることが必要です。
しかし、故人の宗派までは把握しきれていないことは珍しくありません。
万が一、正しい作法がわからない場合は、先んじて焼香を行う喪主や親族にならうのがよいでしょう。
家族葬では、一般葬とは異なり、閉式後に精進落としの場を設けない場合もあります。
その場合は、喪主や親族の負担を考慮して長居することなく、簡単にお声がけしたうえで帰宅してください。
ここまで、家族葬に参列する際のマナーを解説してきました。
故人の家族葬が執り行われる旨を伝えられた方としては、「家族葬へ参列してもよいのだろうか」と判断がつかない場合もあるのではないでしょうか。
以下では、参列の可否を判断するための基準を解説します。
訃報を受けた際に、喪主側から参列してほしい旨を伝えられた方は、家族葬に参列できると判断できます。
また、受け取った葬儀の案内状に日時や場所が示されており、参列を控えてほしい旨の記載がない場合も、家族葬に参列が認められる可能性があります。
ただし、これだけでは「参列してほしい」という明確な意思表示と判断するのは難しいため、喪主にあらかじめ確認するのがよいでしょう。
家族葬に参列する要望を受けていない場合や、案内状に参列不要と記載されている場合は、たとえご自身が故人と親しい仲であったとしても、参列することは叶いません。
家族葬は、生前の故人やご家族の意向で参列者の範囲を決定します。
万が一参列できない場合は、故人をささやかにお見送りしようとする喪主側の気持ちを尊重して、参列を控えましょう。
たとえ訃報を受けたとしても、「葬儀を親族のみで執り行う」と伝えられた場合は、参列を控えてください。
また、人づてに故人が亡くなったことや葬儀が行われる日時・場所を知った場合でも、喪主から直接連絡が来ていないのであれば、参列を控えるのがマナーです。
ここまでお話しした通り、家族葬では喪主側の要望がなければ参列できません。
しかし、家族葬に参列しない、もしくは参列できない方のなかには、後日弔意を示そうとお考えの方もいるのではないでしょうか。
以下では、こうした場合に故人を偲ぶ気持ちをご家族へ伝えるために守るべき3つのマナーをご紹介します。
【家族葬に参列しない場合のマナー】
お悔やみの電話でご家族に弔意を伝えるタイミングは、家族葬を終えて落ち着いた頃合いが望ましいです。
家族葬に参列しない場合は、弔意を速やかに示すために、タイミングを考慮せず電話しようと考えてしまうかもしれません。
しかし、家族葬を執り行う前後に電話をかけると、心労のなかにある喪主・ご家族に対して、余計な気を使わせてしまうことになります。
そのため、お悔やみの電話を行うタイミングは、家族葬が執り行われて1週間程度経った頃が適切だと考えられています。
なお、電話をかける際はお悔やみの言葉を簡潔に述べ、長電話とならないように配慮しましょう。
香典や供花、弔電を送りたい場合は、家族葬の案内に、これらの可否が明記されているのかどうかを確認してください。
万が一、香典や供花、弔電を辞退しているのにもかかわらず一方的に送ると、喪主の対応を増やし、故人とのお別れの時間を奪ってしまいます。
特に香典や供花は、後日の対応のほか、家族葬における喪主側の自己負担額を増やす一因となりえます。
そのため、香典や供花、弔電で弔意を示したい場合は、あらかじめ喪主に確認しておくことが大切です。
なお弔電については、案内状に特記事項がなくても失礼に当たらないとされているので、喪主側から明確に辞退する意向がない限りは送っても問題はないといえます。
葬儀後の弔問は、喪主側の意向を確認したうえで行うように心がけてください。
喪主やご家族のなかには、時間をかけて故人を偲びたいと望んでいる方もいらっしゃいます。
後日の弔問を望む場合は、家族葬の1週間後から四十九日を迎えるまでの期間で弔問の可否を確認し、了承を得たうえで訪ねることが大切です。
家族葬は、喪主側の意向で柔軟に執り行うことができる形式の葬儀です。
落ち着いて故人を偲ぶことができる一方、慣習を重んじる方に抵抗感を与える可能性があるため、喪主は周囲の気持ちを理解するように努め、丁寧に対応することが大切です。
参列者は、喪主の意向を尊重し、負担を増やさない行動を心がけましょう。
家族葬に参列しない方も、一方的に弔意を示すことなく、喪主の心情を思いやり、適切な順序を踏むことが必要です。
大阪市の東住吉区・天王寺区・生野区で家族葬を検討している方は、「家族葬おくりみ」へご相談ください。
1日あたり1組だけが利用できる斎場で、気を使うことなく、ゆっくりと故人をお見送りできる葬儀を提供いたします。
株式会社川上葬祭 代表取締役
<資格>
<略歴>
創業明治10年の老舗葬儀社、川上葬祭の5代目
関西大学卒業後、テニスコーチとして就職。その後、家業である川上葬祭へ入社。
代表に就任以降、業界の異端児として旧態依然の業界改革に着手。その経営手法から葬儀社向け経営コンサルティングや、業界向けセミナー講演活動、一般消費者向けの「無料お葬式講座」を講師として17年以上、現在もなお続けている。
ご葬儀は大切な儀式であり、プランや費用は様々です。事前相談をお勧めいたします。
事前にどのようなお葬式にされたいのかご認識いただくことで、いくら掛かるのかが明確になり、ご不安が解消されます。不必要な物を取り除くこともできます。
事前相談ではご家族様のご希望やご相談を丁寧にお伺いする事が出来ます。その物語からわたしたち「家族葬おくりみ」のスタッフが世界で一つだけのお別れの刻を提案いたします。
よくあるトラブルに「見積より支払い金額が多くなった」「希望の葬儀と違った」ということがあります。事前相談で金額、内容が適切かどうかチェックすることができます。
ご家族様に最適な資料をお送りさせていただきます。資料は葬儀社とわからない、無地の封筒でお送りすることもできますので ご安心ください。またいただいた個人情報は資料の送付とその確認の際のみに利用させていただきますので ご安心くださいませ。
資料請求で届くもの
お葬式プラン / 式場のご案内 / ことほぎ友の会のご案内 等
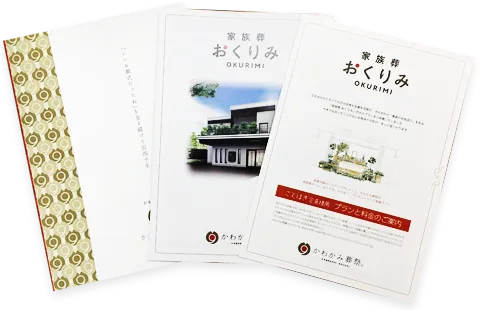

ご来店以外にご希望場所までお伺いする事も可能です。その際ご指定場所をお知らせ下さい。

お電話にて不明な点等ご相談承っております。24時間365日いつでもご対応させて頂きます。

メールでもお気軽にご相談いただけます。まずは不安や疑問点から一緒に解決しましょう。
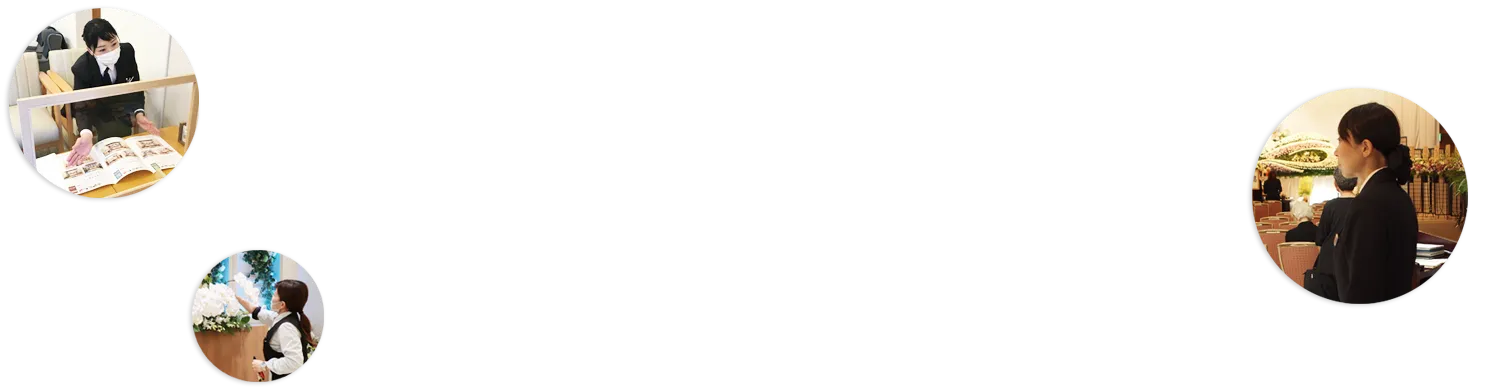
私たちは、常に、お客様の立場に立ち、喜んでいただけるご葬儀を提案・実現いたします。
品質の確かなお葬式を、地域の皆様にご提供しております。
式場においては、1日1組の葬儀式場で、気を遣うことのないゆっくりとした大切な人とのお別れをご提供しております。
価格においては、不透明なお葬式費用を無くし、明朗会計を実施してまいりました。
おくりみは、今後もお客様に喜んでいただくことを第一に、日々、精進してまいります。
大阪市|東住吉区・天王寺区・生野区の、家族葬・お葬式の相談窓口は「おくりみ」へ。JR桃谷駅から徒歩5分。桃谷商店街からもアクセスが便利な「桃谷本店」 今里筋と勝山通の交差する大池橋交差点、大池橋バス停の目の前「大池橋店」お葬式や家族葬の相談、事前の費用見積り、準備や手続きのこと承ります。
無料のお持ち帰り資料(生野区優良葬儀場パンフレット、お葬式の手引き、お葬式のマナー他)を多数、取り揃えております。
最寄り駅:生野区の各駅・・・JR桃谷駅、鶴橋駅、東部市場前駅、近鉄・鶴橋駅、今里駅、大阪メトロ千日前線鶴橋駅から乗り継ぎアクセス良好。